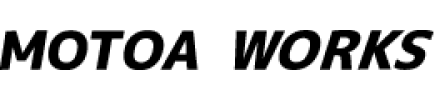施工事例

2025.05.31
キレイなRS/Z
クラッチワイヤー交換

クラッチペダルに違和感を感じると言うコトで入庫。
4WD用は販売終了してしまいましたがFF用は健在!
というコトでワイヤーを新品交換していきます。
新品の純正クラッチワイヤー。
交換前の調整部分。
調整ナットが逆向き+ダブルナットによる完全固定。
振動の多い悪路を散々走ってもここが緩んだ事など一度も無いので、緩んでしまう原因はただ一つ。
クラッチレバーの遊びが過大なところで調整ネジを止めているから。
レバーを押してワイヤーに張りが出る位置まで締めないと緩むのも当然です。
多分、ペダル操作でのクラッチが切れる位置の好みが反映された結果だと想像しているので特にどうこうはありませんが、たまにクラッチが摩耗し遊びが無くなって来てしまったからか、レバー位置を変更されているミッションを見る事があります。またワイヤーを保持するブラケットが破損し、必要以上にワイヤーが手前に来ているミッションも。
そうなると場合によっては調整ネジ山を目一杯使ってもワイヤを張る事が出来ず、緩んでしまうのでダブルナットで対策なんて事もあり得る話。
そんな色々があるので、最低でもレバー位置が適正か、ワイヤブラケットは正常か、この2点は確認しておいた方が無難です。
通常、何かに干渉しえる部分にはスポンジが巻かれたり等、干渉によるトラブルを未然に防ぐ施工が施されています。
FFのアルトをほとんど見ないからか、干渉対策がされていない部分に干渉痕があるのを発見。
4WDでは一度も見た事がないので、FF特有なのか取り回しに不備があるのか、正直原因は不明です。
干渉していたメンバーはもちろん、ワイヤーも硬い部類に入ります。
硬いモノは振動を吸収する事が出来ないので、ある周波数の時ブルブルと震える時があり干渉痕が広がったと想定。
その改善策としてかつみんが実施したのがゴムホースを巻きつける手法。
ワイヤがブルブルする隙間を減らすだけでなく、振動吸収能力が高いゴムを使用する事でワイヤ自身がブルブルしなくなる可能性も出て来ました。
本当にちょっとした事ですが、振動対策や干渉対策は部品の寿命を左右する大切な作業です。
純正部品であるクラッチワイヤでさえも、ウン十年と言うメーカーが想定している使用期間を大幅に超えて使用すれば、トラブルが起きるのも仕方の無い事。
たかがクラッチワイヤー交換ですが、されどクラッチワイヤー交換です。
これで違和感ともおさらば!
と思っていたのですが、多少は改善されたけどまだ・・・とかつみん。
この違和感の正体がワイヤなのかクラッチなのかの判断って、実は意外と難しい。
大概はレリーズベアリングが摺動する部分が滑らかでない事が違和感の原因。
たまにクラッチディスクのスプリングが外れた事による違和感。
そしてワイヤー内に水分が浸入しサビ発生による違和感。
今回はワイヤを単独で動かすと十分渋さを感じたので、両方出ていた事になりますが、違和感のみの修理であれば先ずはワイヤ交換。それでも直らなければクラッチ交換である事をお客さまと共有する必要がある不具合です。
というコトで、このままクラッチ交換へと作業を進めて行くのですが、そのあたりの作業は次回にするとして、振動&干渉対策のお話をして来ているので、最後はエンジンを降ろす過程で発見したインタークーラーのお話で締めたいと思います。
CA71Vはエンジンを降ろさずともミッションだけを降ろす事が出来たので、30分掛からずにクラッチ交換なんて事も出来たのですが「スズキ時代は競争していました(笑)」CL系からメンバーやマウント形状が変わり、エンジン&ミッションのまま降ろした方が早いという時代に。「ちなみに今回のH系までCL同様の方式が採用されています」
まぁ、今は早く「速く」よりも、どこか想定外の不具合が起きていないかを探し対策する事に重点を置いているので時間は食われますが、古いクルマを整備するとはそういうコトなのです。またアルトはオーナーから特別な愛情を注がれているケースが多いクルマでもあるため、そのあたりの見極めも大切な作業の1つです。
信頼してくださるお客さま限定のサービスの様なモノです。
社外インタークーラの固定部分。
エンジン側のステーとインタークーラステーが直に触れているのが分かります。
これが純正だと結構な厚さのゴムを介してラバーマウントされています。
純正がわざわざしている事には意味があるはず。
なぜならコストを考えれば出来るだけ部品点数を減らすのが常だからです。
つまりインタークーラは振動に弱い可能性があるというコトです。
そう考えると、同じような機構であるラジエータもエアコンのコンデンサもラバーマウントです。
エンジン側のステー。
えらくオイルっぽいです。
どうやらインタークーラにダメージがある様子。
これだけオイルっぽいというコトはタービンからオイルも一緒に供給されている様です。
ただでさえ狭い空間に装着されているインタークーラなので、大型化しただけでも干渉によるリスクが増大します。
干渉対策と振動対策を確実に実行するにはエンジン側のステーを見直すところから始める必要もありそうですが、果たしてそこまで時間を浪費して装着する必要があるのか?というトコロです。
550初期のジムニーにインタークーラ無しと有りが年式違いで存在していたのですが、有りバージョンの速さは衝撃的でしたが、無しバージョンの遅さにも衝撃を受けた事を今でも覚えています。
また同じF6AツインカムのRS/Xとカプチーノを乗り比べた時もそう。
明らかにRS/Xの方が速いと感じるのですが、速さ、今回で言うなら加速感と言えばよいのか、アルトの方が速く感じるのはインタークーラ配管が短い事によるレスポンスの良さから生み出される加速感であり、意図してメーカーがワークスに施した味付け。一言で表すならやんちゃ感(笑)
そしてカプチーノを一言で表すなら上質感。
当時はアルトの方が軽快で速いじゃん程度の認識でしたが、今は旧規格にも関わらず、軽自動車の枠を超えた大人のスポーツカーです。
これはSR-FOURにも通じるところがあるのですが、速いクセにそこを強調していない味付けである事自体、何とも贅沢なクルマです。
社外品の様な壊れ方を一度も見た事が無い純正のインタークーラー。
お陰で在庫置き場にゴロゴロしています(笑)
キャニスターのホース。
PDFはこちら
カテゴリ
アーカイブ